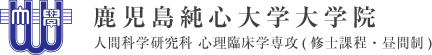カリキュラム
関連ページ一覧を表示
本学大学院のカリキュラムは、「こころ(精神)」と「からだ(身体)」の両面から、より深く高度な知識と技能を獲得することができる特色をもっています。
そのため、本学では養護教諭の専修免許を取得することも可能(養護教諭一種免許状取得者のみ)です。
開講科目一覧
特別研究
- 特別研究Ⅰ
- 特別研究Ⅱ
専門領域
- 臨床心理学特論
- 臨床心理面接特論 I(心理支援に関する理論と実践)
- 臨床心理面接特論II
- 臨床心理査定演習 I(心理的アセスメントに関する理論と実践)
- 臨床心理査定演習II
- 臨床心理学研究法特論
- 心理統計法特論
- 被害者臨床援助特論
- 福祉行政総論
- 障害児 (者) 心理学特論
- 小児保健特論
- 精神薬理学特論
- 遊戯療法特論
- 精神分析的面接特論
- 文化人類学特論
- 神経学特論Ⅰ・Ⅱ
- 福祉分野に関する理論と支援の展開
- 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
- 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
- 保健医療分野に関する理論と支援の展開
- 教育心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開)
- 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
- 心の健康教育に関する理論と実践
課題研究
- 臨床心理基礎実習
- 心理実践実習Ⅰ
- 臨床心理実習Ⅰ(心理実践演習Ⅱ)
- 臨床心理実習Ⅱ
シラバス一覧
ピックアップ授業
被害者臨床援助特論

-
鹿児島8.6水害、阪神淡路大震災、東日本大震災、 熊本地震等の自然災害をはじめ、犯罪被害、DV、 虐待などの人的災害への緊急支援・カウンセリング 事例等を取り上げます。
心の健康教育に関する理論と実践

- 心の問題は人間一般に共通する問題でもあり、その 予防や啓発活動の実践が望まれています。様々な 領域、現場における心の健康教育に関する高度な 理論や実践を学び、心理援助職としてどのような 実践を行うことができるかについて考えていきます。
臨床心理基礎実習

- 心理臨床家としての基本的態度を習得するために、 守秘義務や倫理、面接の技術や記録作成方法を 学びます。また、実践的な学びとして面接のロール プレイなども行います。
こんな授業をしています
授業紹介「臨床心理査定演習」 修士課程2年 Mさん
今回、紹介したい授業は「臨床心理査定演習」です。その中で取り上げられる”ロールシャッハ・テスト”は、人間のパーソナリティを立体的・統合的に理解するものです。
この演習ではまず、自己洞察をします。この体験を通して、私は「相手の問題ではなく私自身の問題なのだ」ということに気づき、気持ちが楽になりました。さらに、相手を理解するためには、多くの知識、柔軟な見方、自分自身の視座(どの立場で見ているのか)が重要だと理解できました。分析は難しいのですが、先生が明快に説明してくださるので、より深く、自分と他者を理解できるようになります。
院生からのメッセージ
人間科学研究科 心理臨床学専攻 修士課程2年 Tさん
本学のオープンキャンパスの講義で「クライエントの”健康な部分”も含めその個人をみる」という言葉に感銘を受けたことが、鹿児島純心大学、そして大学院に進学する決め手となりました。
大学院では、臨床心理士・公認心理師資格取得のための講義や実習、仲間と協働する学校行事等、クライエントをはじめ、先生方や仲間から多くのことを学んでいます。
地球規模で刻一刻と状況が変化する今、自他の心を大切にすることがより求められると思います。
自身の感覚と向き合いながら、ありのままの姿でクライエントと共に歩むことのできる心理臨床家を目指しています。
学位論文審査基準
修士論文題目一覧
令和6年度
- 児童養護施設の被虐待児における親の捉えなおしの検討-心理療法担当職員の語りから-
- アウェイ育児を経験している子育て世帯の個別性と育児支援資源ニーズの検討―A市の子育て世帯に焦点を当てて―
- 青年期の恋愛関係と親子・夫婦関係について-信頼感・依存性に焦点を当てて-
- A市における発達支援体制の現状と課題-当事者の語りからの検討-
- DV行為者における心理プロセスの検討-DV加害者プログラムの参加者の語りから-
- 摂食障害の心理的特徴と心理面接の継続の困難さの関連性についての検討-心理専門職者の語りから-
令和5年度
- 新任教師の心理プロセスの検討-心理プロセスから見た心理的支援-
- 奄美大島大和村における壮年期以降の主観的幸福感に関する心理学的研究
- 認知症者の家族の適応プロセスについての検討~社会的支援と関係性に焦点を当てて~
令和4年度
- DV被害者支援における女性の心理支援者の共感疲労について
- COVID-19状況下における大学生のメンタルヘルスと首尾一貫感覚の関連について
令和3年度
- 大学生個別指導塾講師が経験する中学生への心理的かかわり-塾講師の心の動きを通した居場所としての塾の考察-
- 生活臨床における心理職の内的体験-児童養護施設における職業的アイデンティティ形成のプロセスに着目して-
- 特別支援学校教員のメンタルヘルスに関する臨床心理学的研究-感情労働下における病気休職することなく勤務しつづけていることの意味を探る-
令和2年度
- 初任セラピストの自己開示に関する質的研究-自己開示に伴う主観的体験およびプロセスに視点を当てて-
- 心理専門職のバーンアウトの予防について-ワーク・エンゲイジメントの視点から-
- 親子間のズレが子どもへ与える影響についての質的研究-心理専門職者が行う親子面接の視点から-
- 妬み感情とマインドフルネスとの関連について-良性・悪性妬みに着目して-
令和元年度
- 青年期における自己存在の価値への気づきの経験について
- 2016年熊本地震により被災した自治体職員のPosttraumatic Growth(PTG)に関する臨床心理学的研究
- 初期統合失調症のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究ー健康な面や成長の可能性から予防的介入を探るー
- トランスジェンダーの人々の自己変容過程における経験についてー心理臨床場面における支援の在り方を考えるー
- 不登校の「居場所」に関する臨床心理学的研究-自我を再体制化するプロセスに視点をあてて-
平成30年度
- 青年期女子のアイデンティティ確立及び母親への愛着が異性態度に及ぼす影響
- 被虐待体験のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
- 被災しながら活動した支援者の感情労働とレジリエンスに関する臨床心理学的研究
-支援者支援の視点から- - クライエントの根源的な問いに対するセラピストの経験
-面接場面における「宗教的」な経験に視点をあてて- - 同性愛者からカミングアウトを受けた被開示者の心理プロセス
-友人と家族に焦点を当てて- - 箱庭を制作者の立場に立って理解する試み
-「箱庭-物語法」を用いて-
平成29年度
- 平成28年度熊本地震における臨床心理学的研究
ー生きがいとレジリエンスに視点を当ててー - 突然の死別経験者の Posttraumatic Growth に関する臨床心理学的研究
―苦悩と精神性的変容に着目して― - 心理療法における非日常についての考察
―セラピストがクライエントのあいだを生きる経験から― - 自己変容に関する自己の捉え方について
ー”変わらない”自分を選択するということに着目してー
平成28年度
- 外国人留学生の支援に関する臨床心理学的研究
―留学生を支援するチューターの感情に視点をあてて― - 自己肯定感と親の養育態度
―成功・失敗体験時における賞賛・叱咤体験に焦点を当てて― - スクールカウンセラーは学校現場での協働をどのように体験しているのか
―担任教師,養護教諭との協働に焦点をあてて― - ライフコース選択による母親の育児負担感
―育児負担感の内容に着目して― - 境界性パーソナリティ障害のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
―身体境界得点を用いた自我境界に視点を当てて― - 心理臨床家の「見立て」はどのように意味づけられているのか
平成27年度
- 加害者の背景にある「被害者性」に関する床心理学的研究
―保護司へのインタビューを通して― - 大学生女子の孤独感に関する臨床心理学的研究
―父娘間・母娘間における「甘え体験」「甘やかされ体験」の観点から― - 青年期における過敏型自己愛傾向とそのメタ認知が精神的健康に及ぼす影響について
- 精神的な傷つき(トラウマ)からの回復に関する臨床心理学的研究
―危険運転致死罪の遺族におけるPTG(Posttraumatic Growth)の在りよう― - スクールカウンセラー(SC)の臨床活動に関する質的研究
―学校という”場”における経験の語りから - うつ状態にある中年期男性のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
―感情カテゴリー(各大法)に視点をあてて―
平成26年度
- 中国語を母国語とする在日留学生の文化受容態度に関する研究
―原因帰属とコーピング方略に焦点を当てて― - 中学生のLINEの使い方とトラブル被害
―自尊感情、インターネット・リテラシーの認識、保護者の制限との関連から― - 家族形成期における源家族の影響に関する経験
―20代既婚女性を対象に― - 子育て支援がもたらす母親の心理的な変化
―育児感情、母親としての自己効力感、抑うつに着目して― - 統合失調症の初期にみられるロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
―「思考・言語カテゴリー」(名大法)に視点を当てて― - アルコール依存症から回復を続けている人の人間関係における経験
―アルコール依存症同士の夫婦へのインタビュー調査を通して― - 自閉スペクトラム症児(者)をもつ養育者の子育てに伴う感情に関する臨床心理学的研究
- 教師のメンタルヘルスとワーク・ライフ・バランスとの関連
―ストレスの緩衝効果の検証― - 女子大学生における自己意識と痩身願望および食行動異常との関連
―痩身理想の内面化に着目して―
平成25年度
- 「生きづらさ」を訴える発達障害のロールシャッハ反応
―二次障害に焦点をあてて― - 本人への障害名の告知が「高機能広汎性発達障害者」へ与える影響
―高機能自閉症・アスペルガー障害と告知された成人男性へのインタビューを通して― - 青年期女子における自己関係づけに関する研究
―自己関係づけの類型化とTATによる質的アプローチ― - 心理臨床家は面接過程においてクライエントへの気がかりな応答をどのように経験しているのか
―問題解決型の臨床心理士を対象に― - 青年期における社交不安障害傾向に関する臨床心理学的研究
―両親の養育態度・きょうだいとの関係に焦点を当てて― - 視線恐怖傾向のある女子大学生にみられる対人関係の諸相
―TAT図版を用いた検討を通して― - 高校生の友人関係とコミュニケーション,いじめ経験,自尊感情との関連
- 親との死別を体験した人に関する研究
―父親を亡くした人の語りから― - 不合理な信念への気づきがもたらす精神的健康への影響
―大学生がもつイラショナル・ビリーフとユーモアの媒介過程に着目して― - 広汎性発達障害児・者のきょうだいに関する質的研究
―同胞との関係についての語りを通して― - 児童養護施設職員に対する心理コンサルテーションプロセス
平成24年度
- 寮生活の経験に関する質的研究
―高校時代に寮生活を送った女性の語りから― - 恋愛関係における葛藤場面で問題言及することへの意味づけ
―青年期女子のジェンダー意識と相手との関係性に対する効力感に着目して― - 心理臨床における共感はクライエントにどのように体験されるのか
―過去の傷つき体験に対する共感的関わりをめぐって― - 自己愛傾向をもつ者の職場での葛藤場面における自己評価
―早期離職を防ぐための支援に向けて― - 嗜癖からの回復はどのように経験されているのか
―アルコール依存症から回復を続けている人たちへのインタビュー調査から― - 過去の食事経験と女子大生の摂食障害傾向との関連
―摂食障害につながるダイエット行動と、食を通した人間関係が子どもに与える影響― - 自閉性障害児(者)親の会に所属する母親と父親に関する臨床心理学的研究
―親の会が主催する活動への参加プロセスを通して― - 青年期の人々におけるコミュニケーションツールとしてのSNS(ソーシャル・ネット・ワーキング・サービス)利用
平成23年度
- 共感的関わりによる面接と音楽聴取が『過去の傷付き体験』にもたらす効果
―気分と記憶量の変化に注目して― - 思春期の高機能広汎性発達障害児における社会情動プロセスの特徴
―P-Fスタディを用いて― - 望ましいリーダーシップ観によって逆説的にもたらされる職場ストレス
―部下をもつ公務員のメンタルヘルス対策に着目して― - スクール・トラウマに関する臨床心理学的研究
―A中学校における臨床心理士の支援事例を通して― - 家族の未解決問題をめぐる親子それぞれの経験に関する質的研究
―青年期の子どもと母親が問題を維持する過程― - ユーモアコーピング生起のメカニズムとその効果について
―ストレッサーの種類に着目して― - 発達障害児の社会性の障害に関する研究
―不器用と場面の認知に焦点をあてて― - 臨床心理士における感情労働に関する臨床心理学的研究
―「自己一致」との関連性に着目して― - 大学生の就職活動に対するポジティブ・イリュージョンの影響
平成22年度
- アルコール依存症およびアルコール関連問題を抱える当事者の家族に関する研究
―家族としての語りから― - 未婚の成人女性とその母親との関係
―サポートの授受による類型化と想定される心理的リスク― - 警察官のResilienceに関する臨床心理学的研究
―Resilienceにおける「意味づけ」と「生きる意味」に焦点をあてて― - 高機能広汎性発達障害児における自己認知
―あるアスペルガー症候群児との面接を通して― - 大学生の反すうに関する臨床心理学的研究
―2つの反すうに関する一考察― - 障害のある子どもの父親であること
-父親の語りから気持ちの変化に焦点をあてて- - 女子大学生の自己愛傾向と友人関係
―友人葛藤場面における応答と“本音”の違い― - 広汎性発達障害児のきょうだいが捉える家族の関わりのあり方
―母親との関係の変化に焦点を当てて― - 育児期にある成人女性が選択してきた各ライフコースの心理的特徴と主観的幸福感との関連
- 公務員の被援助志向性に関する研究
―被援助志向性を抑制するパーソナリティ要因に焦点を当てて― - 子育て支援活動に参加する子育てを終えた女性の世代性
―子育て経験の成熟のプロセスに焦点を当てて― - 非主張的自己表現の捉えられ方についての研究
― 受け手のコミュニケーションスタイルに着目して ―
平成21年度
- 死別への意味づけと時間的展望に関する臨床心理学的研究
- 過去のいじめ経験が現在の対人関係に及ぼす影響
―いじめ当事者認知と同調性に着目して― - 祖母の子育て参加における子育ての捉えなおしに関する臨床心理学的研究
- 不登校経験者のきょうだいにとっての不登校
―自身の経験をどのように意味づけるのか― - 就学移行期を通した広汎性発達障害児の母親の心理的変化
―社会的支援と子どもの捉え方及びその関連― - アグレッションの肯定・否定的側面及び方向性を測定する尺度作成の試み
―大学生の場合― - 高齢者のソーシャルネットワークと精神的健康との関連
―ソーシャルネットワークの違いがもたらすライフイベント、健康状態からの影響過程の相違― - 青年期の自立をめぐる家族機能とストレスの関連
―家族ライフサイクルの視点から― - 教師の児童生徒に対するかかわりを規定する要因
―教師独自のストレッサーと教師観に着目して―
平成20年度
- 子育て期の母親の自己効力感に関する臨床心理学的研究
―今後の子育て支援のあり方の模索― - 青年期女子の心理的両性具有に関する臨床心理学的研究
―家族関係、友人関係に焦点を当てて― - 養護教諭の自己効力感と相互独立性―相互協調性の関連および被援助志向性への意識
―スクールカウンセラーとのコラボレーションに焦点をあてて― - 情緒障害児の家族病理と親子関係に関する臨床心理学的研究
~神経症的登校拒否に視点をあてて~ - 職場ストレス状況における「やりがい」とそれに対する「コーピング」に関する臨床心理学的研究
- 高齢者の痛みの語りから
―主観的幸福感に焦点を当てて― - 心を“くすぐる”コンプリメントに関する臨床心理学的研究
~居心地と問題のとらえ方の変化に焦点をあてて~ - 被虐待体験をもつ高校生のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
平成19年度
- HIV/AIDSに関する臨床心理学的研究
~基礎知識・関心と受容性との関連に視点をあてて~ - 職場ストレス状況におけるコーピングと心理的ストレス反応に関する臨床心理学的研究
~抑うつに視点をあてて~ - 消防職員のストレスに関する臨床心理学的研究
―CIS(Critical Incident Stress)に視点を当てて― - 子どもの不登校を経験した母親に関する臨床心理学的研究
―不登校児童・生徒の母親の語りから― - 救援者のストレスとその回復力に関する臨床心理学的研究
~いわゆるResilienceに寄与する要因について~ - 警察官のSecondary Traumatic Stressに関する臨床心理学的研究
~ストレスコーピング及び性差に視点をあてて~ - 特別支援教育に関する臨床心理学的研究
―保護者の「障害受容」に視点をあてて―
平成18年度
- しつけ場面における母親のたたく行為とその規定要因に関する臨床心理学的研究
~STAI得点、生育歴、育児観との関連~ - 境界性パーソナリティ障害のロールシャッハ反応に関する臨床心理学的研究
―トラウマの軌跡を探る― - 児童生徒の自殺予防に関する臨床心理学的研究
―自殺念慮の「背景」と「援助」のありようについて― - 教育現場における心理臨床家の役割に関する臨床心理学的研究
―不登校に焦点をあてて― - 消防職員のストレス(CIS、PTSD)に関する臨床心理学的研究
- 鹿児島県の児童生徒の精神的健康に関する臨床心理学的研究
~精神的健康・生活習慣と不登校の関連に視点をあてて~ - 母親が子どもに抱く否定的感情に関する臨床心理学的研究
―感情的に叱った後の心の変化と子どもとの関係の深まり―
平成17年度
- 自閉性障害における「心の理論」と“ふり”遊びについての臨床心理学的研究
- 自閉性障害児に関する臨床心理学的研究
~M児との遊戯療法を通して~ - 自閉性障害者の親の障害受容に関する臨床心理学的研究
- 児童・生徒の精神的健康に関する臨床心理学的研究
―「20年の経時的変化」と「友人に対する意識との関連」に着目して― - PTSDのアセスメントに関する臨床心理学的研究
- 身体疾患を抱えた高齢者の「生きる意味」に関する臨床心理学的研究
―「病、死、家族」に対する意味づけに視点を当てて― - 広汎性発達障害児へのアセスメントに関する臨床心理学的研究
~行動観察に焦点を当てて~ - 自閉性障害児をもつ母親の心理変容過程に関する臨床心理学的研究
- 選択的緘黙の基本概念に関する臨床心理学的研究